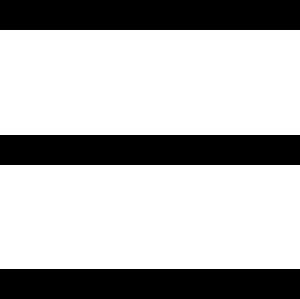チョプラ・ジョナスが回想録を書こうと考えていたとき、彼女の計画は人々に行間を読んでもらうことでした。「最初、この本は若い頃の自分に宛てた一連の手紙だと思っていました」と彼女はZoomで私に語った。ロンドンの1月中旬の夕方、チョプラ・ジョナスはツートンカラーのシルクシャツを着て、髪を顔にかかるように後ろに引っ張り、燃え盛る大きな暖炉の前に静かに座っていた。
「2020年の初めに、自分の功績や栄誉について話し、若い頃の自分にアドバイスを与えようと考えてこのプロセスを開始しました。表面をなぞって、人生のより困難な部分をさらっと読み流そうと思ったのです」と彼女は、自分の世間知らずさに首を振りながら、乾いた口調でこう語る。しかし、彼女が座って書くと、出てくるものはそうではありませんでした。「そのプロセスは日記を書くことに似てきました」と彼女は言います。「あらゆることについて考え始めると、書くことは自分の感情、失敗、痛みを分析することになりました。何年も考えていなかったほど、あるいは思い出していることにさえ気づかなかったほど、たくさんのことが私から流れ出てきました。」
彼女の自伝『Unfinished』に完全に没頭するという課題。適切なタイミングで来ました。「私はエンターテインメント業界に身を置いて20年を迎えようとしていたので、それを個人的に認めておきたかったのです」と彼女は説明する。「私はまた、自分の人生を内省的に見つめることができる十分な自信を持っている場所にいることに気づきました。これらのことが起こっていた当時、私にはそれができなかったことです。」

軍医の子として生まれたチョプラ・ジョナスは、陸軍基地を転々としながら育ちました。「そして大人になった私は、常に一つのプロジェクトから次のプロジェクトへと走り回っていました。過去を振り返って熟考する時間はまったくありませんでした。」私はうなずき、過去 20 年間、70 を超えて数え切れないほどのボリウッドでの彼女の役を思い出しました。「常に次のことを考えていました。いろいろな意味で、私は人生のほとんどを自分自身から逃げてきたように感じます。」
形式どおり、私たちの会話は、セリーヌ・ディオンとスコットランドの俳優サム・ヒューアンが共演するソニー・ピクチャーズのロマンティック・コメディ『テキスト・フォー・ユー』を終えたばかりのチョプラ・ジョナスの直後に始まりました。ほとんど休憩を挟まず、ショーランナーチームのルッソ兄弟のために俳優リチャード・マッデン(『ボディガード』、『ゲーム・オブ・スローンズ』)とともにアマゾンのシリーズ『ザ・シタデル』の仕事を始めようとしている。このプロジェクトのため、彼女は11月までロンドンに駐在することになる。「私の仕事には一貫性を保つ余裕はありません」と彼女は言います。「だから、新型コロナウイルスが起こったとき、私は座って、長年溜め込んでいたものに取り組む必要に迫られました。」
チョプラ・ジョナスにとって寄宿学校は、もう一度訪れる必要があると感じた感情的な場所でした。「3年生で学校に行かされたことはもう寝かせたと思っていましたが、この本のために和解せざるを得ませんでした」と彼女は私に語った。故郷のバレーリーから電車で4時間、インドのラクナウにあるラ・マルティニエール女子私立学校に通った最初の週、彼女は学校の校庭にあるメリーゴーランドに、冷たくてさびた鉄格子を握りしめながら座っていたことを思い出す。目は門をしっかりと見つめていた。彼女は母親に戻ってきて家に連れて帰るように言いました。「私が鮮明に覚えているのは、見捨てられたという感覚、それは長い間続いた感覚です。」チョプラ・ジョナスさんは、何か月にもわたる心痛(身体を悪くするエピソードを含む)と、母親とのしがみついた訪問を経て、進歩を遅らせた後、ゆっくりと適応し始めたと語った。

しかし、感情としびれの間のシーソーが治まっても、混乱は残りました。「なぜ自分が追い出されたのか理解できませんでした」と彼女は言う。「なぜ彼女がこれほど頻繁に訪問できなくなったのかも理解できませんでした。」チョプラ・ジョナスさんは、弟のシドの登場が母親の注意を奪ったと非難した日もあった。別の日には、彼女は自分の「悪い行動」のせいだと言い、癇癪が24時間体制の規律を決定するきっかけになったのかもしれないと回想した。「母は私を寄宿学校に通わせた理由を説明しませんでした。おそらく母自身がその理由を十分に理解していなかったせいでしょう」と彼女は書いている。最終的に、チョプラ・ジョナスさんは、なぜ自分が追い出されたのか疑問を抱くのをやめ、ここに落ち着き始め、歌、ダンス、演劇、講演などの課外活動に精を出し始めた。これは、これから起こることの兆しだ。彼女には親しい友人もできました。「考えたこともありませんでしたが、もしかしたらそれが私に、自分が望んでいたとは知らなかった安定感を与えてくれたのかもしれません」と彼女は語ります。
この寄宿学校はまた、チョプラ ジョナスに独立の味を与えました。それは、彼女が十代の頃にもっと望んでいたものでした。13 歳のとき、母親と一緒にアイオワ州シーダーラピッズの親戚を訪ねる初めての海外旅行中に、いとこの高校を訪問したときに見た自主性の感覚がとても気に入りました。「インドでは学校では制服を着ますが、アメリカでは自分の好きなように服を着ることができました」とチョプラ・ジョナスは言います。「女の子たちは化粧をして髪を下ろしていました。彼らは短いスカートも履いていました。それはとても刺激的でした。」キラン・マシ(母方の叔母)がシーダーラピッズに住んで学校に通いたいかと尋ねたとき、チョプラ・ジョナスさんはそれについて考える必要はなかった。アメリカは彼女が探していた自由というブランドを提供してくれるからだ。彼女は今回、家を離れることを恐れていませんでした。「本当に、それは私の教育における次のステップのように感じました。寄宿学校がアメリカへの準備を整えてくれたような気がしました。」
それが彼女に準備をさせなかったのは、彼女の新しい生活に影を落とすいじめと人種差別でした。マサチューセッツ州ニュートンで彼女がヴィムル・マム(母方の叔父)とその家族と一緒に暮らしていた2年生のとき、9年生の同級生と彼女の「ヤジ」集団がチョプラ・ジョナスを狙い始めた。最初、彼女は人種差別的な中傷や何気ない押しつけを無視するために最善を尽くしました。「バスに乗るのをやめたのは、彼らが乗ると分かっていたからです」と彼女は本の中で書いています。「たとえ授業が長かったとしても、私は別のルートで授業を受けました。私は彼らがロッカーに集まる場所から離れました。」チョプラ・ジョナスさんは1年間、自分で状況をなんとかしようと努めたが、自尊心は傷ついた。「振り回されたり、女子トイレで私について下劣なことが書かれるのを見るのにはうんざりしていました。」彼女は母親に電話して、家に帰りたいと言いました。「私はアメリカと別れました」と彼女は私に言いました。
「アメリカと決別した」
この経験により、チョプラ・ジョナスさんは、ホームコメディに誘発された、知っていると思っていた国への子供じみた熱狂から目覚めました。しかし、彼女は逃げる機会があったことに感謝している。「このような状況に陥っている子供たちはたくさんいますが、彼らには私がそのような状況から抜け出すという選択肢はありません」と彼女は言います。「辞めることができて、それに対処する必要がなかったのは幸運だった。もし残っていたら、実際以上に私の自信は傷ついていたかもしれないと思います。両親のサポートと安全のもとに家に戻ることができて幸せだと感じています。」
しかし彼女は、「それに対処する必要がない」ことが必ずしも祝福ではないことを知っています。2013年に父親ががんで亡くなったとき、チョプラ・ジョナスさんは自分の悲しみを深く見つめたり、向き合ったりすることはなかったと語る。「代わりに、私はただ力を合わせて乗り越えました。」彼女はインドの女子ボクシングチャンピオンの実話を描いたインド映画『メアリー・コム』のタイトルロールのトレーニングを終えたばかりだった。「仕事で気を紛らわすのが私の常套手段でした」と彼女は手のジェスチャーで強調した。「どんな心の痛み、失敗、悲しみ、喪失感があっても、私はいつも自分の仕事に向き合いました。必要なときはいつでも仕事に夢中になりました。私はダチョウのようでした。いつも砂の中に頭を埋めるだけでした。」